日本時間2022年11月29日現在。
2022年2月24日(その前からうすうす予感が脳裏に走っていたが)ロシアによるウクライナ侵攻が始まり、僕は今年、趣味のロックバンドDIG収集にやる気が薄れた。
それは、2020年コロナ上陸当時のコロナによる世間の異常な空騒ぎの時もそうだった。
僕は、リアルタイムに発信される音楽藝術、生活を写したロックミュージックに、そのジャンルや歌の傾向から「時代」というものを見出そうと思っていた人間だったからだ。

だけど、今回の戦争とコロナが違うと言える点は、コロナは我々の日常社会とゼロ距離で密接している問題であり。戦争は少なくともテレビ越しスマホ越しという距離の問題がある。
今思い返すと、コロナショック当時、アーティストたちのことを考えて、「この人達もコロナの中、バンドの仕事も危うくなってるけど、それでもライブを演ってんだな」と思えるようになった。
それに、ライブのMCや、ステイホーム運動に連動したサブスク解禁や、CDが流通しないからyoutubeに一定間公開するだとか。そしてTwitterにインスタのような、生活に密接したメディアを通じてコロナ禍のミュージシャンの心の渦中を発信するとかで、彼らの裡を知り、コロナ禍の中に呑気なラブソングを歌うバンドをチャラいとかは思わなくなった。コロナ厭戦ムードの現状もあるかもしれないが。
彼らは新型コロナウイルスに直接的打撃を与えられた存在だ。
彼らの多くが作る2020年以降のラブソングは、コロナの空気感とシンクロしていると思う。
東京のどこかのスタジオで、マスクで機材搬入しレコーディング。感染拡大を止めるために必死でライブハウスはカンパを求め、マスクを付けた観客の顔を直視して音楽を演る。
Spotifyで検索すれば面白いほどコロナの音楽(UVERworldを除く)が検索される笑 コロナ禍の歌だったら、THE BLUE HARBの「2020」、eastern youthの「2020」、秋田ひろむ「令和二年」が好きですね
だけど、ロシアによるウクライナ侵攻は違う。海の向こうで戦争が始まる。

僕の聴いている音楽圏―インディーロックとメジャー洋楽、にはロシアへの反戦のアティテュードが、なかった。
洋楽から話そう。
もちろん、U2の支援チャリティーライブや、ピンクフロイドのチャリティーアルバムが出たことは知っている。
しかし、それらはツウな人しか知らない情報だ。探れば、海外アーティストではこのような活動を行っている人は多いかもしれない。
だけど、朝のニュース番組には取り上げられないし、音楽情報サイトでメジャーな記事にはならない。
インディーネイティブhttps://www.indienative.com/で洋楽インディーシーンの動向を探っているけれど、まだ小規模のグループにも、ウクライナのことはあまり関心がないように感じる。
日本人アーティストにしろ外国人アーティストにしろ、ウクライナ問題へのアプローチはコロナ禍より極めて困難だ。
「それは政治的な意図があるから、政治には触れない方がいい。」という腑抜けた物言いからなのか。
じゃあなぜ、かつてのアメリカの政治を大批判して、合衆国の国旗を逆さに飾った、デッド・ケネディーズとか、ブラック・フラッグとか、バッド・レリジョンとか、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンとか、グリーン・デイのアメリカン・イディオットとかがあったんだ?
日本の話だが、イラク戦争当時。向井秀徳氏によれば「音楽に政治を持ち込まない」と長々と回答していたそうだ。
それは逆説的に「向井秀徳さんはイラク戦争反戦ソングをやらないんですか。やるべきですよ。」と、日本の有名ロッカーに対する期待があったのだと感じる。(あのあたりの時代のロッキングオンとかは私は知らない世代なので、この行はあくまで推測。ただそういうやり取りがあったのは確か)。
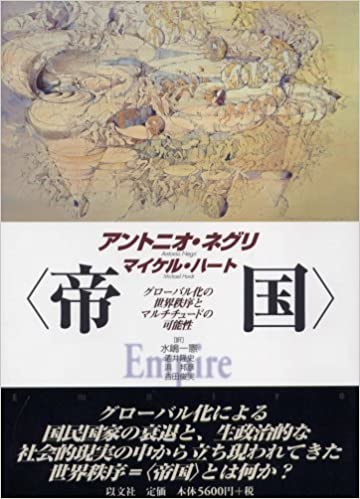
あの頃のカウンターカルチャー界における反戦運動は、『帝国とマルチチュード』に集約される。
簡単に言えば、アメリカという超大国の戦争に対して民草が社会運動するようなものだ。
ゆえに当時、この本はヒットしたそうな。
イラク戦争時のアメリカ人たちは、「戦争を始めることによって自国が堕した」という音楽を作っていた。反戦ソングをあげると枚挙にいとまがない。
だが、今のアメリカ人はロシアを批難しない。それは、東側や西側の意図のどちらが正しいのか分からないから、ではないと思う。
なぜなら、西側諸国に住んでいる、アメリカ人もイギリス人も日本人も、『<帝国>とマルチチュード』の関係にあるからだ。
『<帝国>とマルチチュード』は、アメリカ、そしてグローバリズムの<帝国>に対して、無力なプロレタリアートのような存在たち―マルチチュード―に人間を区分した一説だ。
西側諸国が覇権を取り、世界のグローバル化が進んで、西側資本主義のイデオロギーが増長するという<帝国>。
そして、そのグローバリズムは、国民と国家の違いがあると述べた思想だ。
しかし、今回のロシアとウクライナの戦争は、どうも東側諸国の旧ソ連の内ゲバに見えてしまう。
テレビではワイドショーでプーチンの蛮行を批難する形式がスタンダード。開戦当初からNHK BSの海外ニュースメディアの映像も観ていたので、西側世界的にも反プーチンというスタンスが、現在世論において支配的であると思う。
しかし、我々はロシアとウクライナの傘下。つまり、東側諸国に、居ない。
我々西側諸国民は、この戦争が何を理由として開戦したのか分からない。「極右政権から自国への攻撃を恐れた先制攻撃」「民族のレコンキスタ運動」「穀物資源の簒奪」etc...分かりやすく説明されても、それで納得はできない。
確かにロシアを批難するのも簡単だ。だが、もっとラジカルに考えると、例えば自分が作曲するときに、ウクライナは被害者だけどロシア兵も被害者で、戦闘指揮官プーチンとゼレンスキーをどう書いて歌い上げるのか、どうしようもできないはずであろう。
よって、世界中のミュージシャン、アーティスト、芸術家、子供からオタク層まで受け入れる作品の作り手の多くが、沈黙せざるを得なかった。
そして悲しくも、『<帝国>とマルチチュード』は、現代社会に通用できなくなった言説ということになる。
非対称戦争、対テロ戦争、世界内戦の時代が21世紀のスタンダードになるかと思いきや、そうはならなかった。少なくともプーチンの頭の中は20世紀だった。そして戦争は20世紀から変わらないものだったと初めて分からせられた。メタルギアソリッドふうに言えば「戦争は変わらなかった。」
僕は、ウクライナが攻撃されてから、呑気なラブソングなんぞ聴く意味あるのかと、正直なところ、そう思ってしまった。
だから僕は、戦争を題材にしている、「ガンダム」や「マクロス」や「ストライクウィッチーズ」のオタク系アニソンを聴きまくってた。
だって、ソッチのほうが明らかにリアルじゃないか。僕は西海岸パンク生まれヒップホップ育ちなので、フェイクを嫌う。
では、現在日本人アーティストは何を歌っているのかにハナシを移す。
日本人のメジャーもインディーも、みんなやっぱりラブソングだった。
歌詞から「きみ」という文字が消えることはなかった。
アメリカのハードコアで政治的な曲なら、苛烈に「おまえ」と歌うところで、「きみ」を歌うしか無かった。
そして、戦争的なニュアンスが入った楽曲を紹介すると
リーガルリリーさんの『恋と戦争』
このアルバムは、バッド・レリジョン的な苛烈な現代批評ではない。
僕の敬愛するバッド・レリジョンが93年に西海岸でリリースしたCD。そのうちの『アメリカン・ジーザス』
話がそれてしまうけど、世界的なエンタメでは、やけに「アメリカン○○」という作品が多い。映画だとアメリカンスナイパーとかアメリカンサイコとかアメリカンヒストリーXとか。
それだけアメリカは世界の中心であったはずなのだ。しかし、バイデン政権になれば世界はフラットになってしまった(僕はトランプ派ではない)。
かくして、アメリカなきグローバリズムでは、古い言葉を使うが「大きな物語」が完全に抹消されており、「小さな物語」の時代に本格的突入したのだと思う。
それもそう。ロシアとウクライナの戦争も、「小競り合い」という見方もできるだろう。そんな、自分の知らない離れた国の小競り合いに、日本人は四六時中かまっていられない。ニュースで今のトレンドは統一教会だそうで。
そのようにして、「大きな物語はなかった」とよく云われる言説が、さらに加速し、さっきのリーガルリリーの曲のように「恋」と戦争の話になってしまうのだ。
やっぱり「君と僕」の時代はビートルズのYesterdayから続く。戦後の日常は終わらないし、東西冷戦もまだ集結していないと僕は思う。中国も巨大な国だ。
コロナウイルス蔓延で宮台真司は加速主義者になったし、今人気者のひろゆきも加速主義者だし、事実、新しい生活様式に変えられた我々の社会も「変化」という「加速」をさせられた(主に在宅ワークやウーバーイーツやメタバースなど)。
ちなみにまた余談になってしまうが、私が信頼している評論家の宇野常寛先生(リツイートと反応してくれてありがとうございます。)の『砂漠と異人たち』という本は面白いよ。
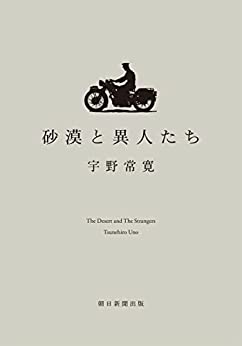
戻す。興味深いケースに、バットマンを挙げようか。

結構こないだ前に公開された『ザ・バットマン』は、明らかにQアノンをメタファーに用いたヴィランを用意していた。しかし、Qたちは世界を変えるわけでもなく、バットマンに倒され、ふつうに終わってしまう。
2019年ジョーカーやダークナイトに反して、風刺をしているようで風刺が出来ていなかった映画だ。なぜなら、世界の問題の渦中にあるQアノンはひどく荒唐無稽だからだ。「地球平面説」なんていう連中と、まともに取り合うなど話にならない。
この映画は、ダークナイトで説かれた「大きな物語」ではなく、「大きな物語を描こうとしたけど小さな物語を描かざるを得なかった映画」になったのだ。
なぜか。Qアノンも「小さな物語」の中を生きているからだ。トランプは小さな物語で票田を獲得しただけにすぎず、それはアメリカの意志ではなかったと、さきの大統領選挙でバイデン政権が発足したことから分かる。
音楽というものは時代を映す。だが、今年の邦楽はなんだかイヤな感じだった。世界問題から逃げるしかない極めて合理的な理由はある。あるのだが、その物足りなさに頭をひねる。
そこで、アニメ界から現れたのが、『連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ』だ。

別にふざけているわけじゃない。これは本当に「時代に合わせてきた」偶然の一致としては出来上がりすぎてるほど完成度の高い作品だった。
第二次世界大戦をモチーフにした世界観で、世界中の部隊が集められ、戦わないで、歌を歌う部隊の主人公たち。彼女らが、戦争というものに直面しながら歌をうたう道を選んでいく、極めて真摯なストーリー。
そして、そのOP曲が、最高に良い。
welcome to the wonderful world luminous
この世界はワンダフルなんだ。
そこがいいんだ。
直球である。そしてこの直球を、少なくともプーチンの頭に投げつけてやりたい。
まさに現代世界をドストレートに風刺できた歌だったと思う。素晴らしい!!!
そして、『ぼっち・ざ・ろっく!』という作品だ。
『ぼっち・ざ・ろっく!』は、読者層の心を鷲掴みにする魅力を盛っている。
厭世的な主人公に、感情移入してしまう。
それはよいとして、音楽性はどうか。
その音楽は、東京に住む一人の孤独な少女のリアルな心情のリリックだった。
確かに、好きなバンドが楽曲提供してるけど、音楽面においては私の愛した いにしえ の『けいおん!』より何手も落ちてしまうように感じ取れてしまう。それは多分僕の耳が老けたせいだろうか。
だが、捉え方を変えると、手落ちではなく、2022年現在の音楽性を見事に引き出しているといえる。
変拍子のリズムに超うまい演奏。そして、最も2022年のトレンドを撃ち抜く一曲一曲。
「リアルさ」と「トレンディさ」を、見事に両立している。
チェーンソーマンでいうと、マキシマム・ザ・ホルモンは中学生の頃から大好きだが、チェンソーマンにマキシマム・ザ・ホルモンは、今の日本の音楽シーンにホルモン並のキワモノがいないんだという事実を突きつけられているようだ。
(マキシマム・ザ・ホルモンは僕の人格形成のひとつにある。超重要バンドです。)
リーガルリリーのくだりじゃないけど、あくまで、小さな物語に生きるしかないのが我々令和人間だ。
しかし、前記事にあるとおり、『けいおん!』の頃は、情熱にあふれていた時代だった。
浅羽通明『ものぐさ精神分析』的な、日本人の精神分析をすると、『けいおん!』の時代は未来に展望があった。震災が起こる前。民主党に「一度任せてみよう」の号令のもとに成り立った民主党政権。東京スカイツリーの建設。お台場ガンダムの建設。『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』で観た、青空のもとエヴァンゲリオンが健康的に全力疾走し、最後はシンジが綾波を助けるという全くもって明るい筋書き。
たしかに2009年のリアルと、2022年のリアルは違うかもしれない。
しかし、それを良いと悪いで区別することは僕は絶対にしない。それでも僕は明日が欲しい。
と、いうわけで、『ぼっち・ざ・ろっく!』は令和の音楽アニメ・漫画として大ヒットを記録している。
CDも、タワーレコードで僕は買った。サブスクにあるけど、サブスクにあるものが全てじゃない。実際に手を取ってCDのドーナッツをレコーダーに加えて再生する。これぞ音楽の醍醐味だ。
そして、買うということはその年に起こった記念物を所持するということだ。
さて、やはり自分の耳が老けたを言い訳にせず、ちゃんとこの『結束バンド』というバンドを聴こうか。